
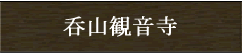
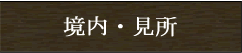
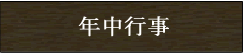
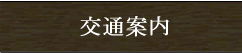
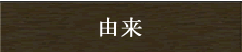
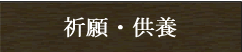
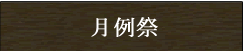
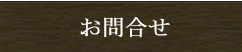
本堂脇に咲く「福聚桜」が、新しく園芸品種として登録されました
呑山観音寺の本堂脇、並びに阿弥陀堂の脇にある桜の古木は、その美しさと場所から春には多くの人を楽しませています。 桜の品種はもとより、鳥が運んで自生したものか、誰かが奉納したものかも不明でした。 八重の山桜と伝わっていたこの桜は寺内で「福聚の桜」という名前で呼び、大切にされてきました。 令和元年、桜の保存や保全活動を行う公益財団法人「日本花の会」の「園芸品種認定制度」を通し、この桜の品種鑑定をお願いいたしました。 調査の結果、どの品種にも該当しなかったことから、令和2年9月に、篠栗町から「福聚桜(ふくじゅざくら)」の名前で園芸品種の申請を行いました。 令和3年3月31日、日本花の会結城農場から田中秀明農場長が来山。
令和3年3月31日の花の調査の様子
福聚桜の特徴 日本花の会「福聚桜」調査報告書より抜粋
(認定番号 第033号)
この桜は福岡県糟屋郡篠栗町萩尾にある呑山観音寺で古くから栽培されており、原木は境内の本堂と阿弥陀堂の隣にあります。 2020年6月時点、樹高は約13m、地表より約1.1m付近で二幹に分岐しており、地表より1.2mでの幹周は131cmと86cm。 樹齢は100年生前後と推定され、過去には台風で太枝が折れる被害もありましたが、今はとても旺盛に成育しています。 類似品種の'金龍桜'(原木所在地:三重県桑名市東方 照源寺)と比較・検討した結果、がく筒の形、がく裂片の形および鋸歯の有無などが異なることから別品種と判断しました。 花弁数が6~11個に増加した小花が一樹中に混在すること、花は大輪で花弁が重なりボリューム感があること、白い花弁と赤茶色の新芽の組み合わせが美しいなど、観賞性にも優れた個体です。 なお、品種名の福聚とは、「福が集まる様」、「福は善のことで善行が集まっていること」、「幸せをもたらす多くの功徳」などを意味する仏教用語で、呑山観音寺が命名しました。
花柄の長さは約2㎝、小花柄は約2cmで無毛。苞全体の形は広倒卵形、鋸歯は芒形。
|

