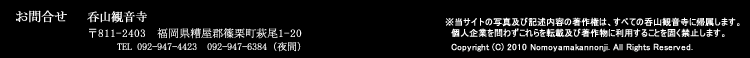呑山観音寺(のみやまかんのんじ)は呑山観音・のみやまさんの愛称で親しまれる高野山真言宗の別格本山です。
霊験あらたかな加持祈祷、お祓いの寺院として、心願成就を祈願するため多くの人びとが参拝に訪れています。
呑山観音寺の山号になっている鉾立山の由来は諸説ありますが、
一説には神代の時代、海津見神(ワダツミノカミ)の娘である玉依姫(タマヨリノヒメ)が、
神武天皇の尊父である彦波剣武鵜茅葺不合尊(ヒゴナミサタケウガヤフキアエズノミコト)に嫁いだ際に
鎮座する山の高さを見比べるため頂上に鉾をつき立てたためといわれています。
その玉依姫ご一行が目的地の竈門山に向うために山を下る途中、山腹に湧く清水を呑み、
渇きをいやしたことから、この場所を「呑山(のみやま)(野見山)」と名付けたといわれています。
また、一説には神功皇后が朝鮮出兵の際、遠く玄界灘を望み
戦勝を祈願して逆鉾を山頂につき立てたとも伝わっています。
呑山観音寺は鉾立山の麓、呑山の地で、山岳信仰・民間信仰の聖地として人びとの信仰を集めてきました。
その後、天保6年(1836年)、四国巡拝の帰りに篠栗に立ち寄った尼僧慈忍の呼びかけで、
篠栗八十八ヶ所が発願され、慈忍の後を受けた藤木藤助たちによって開創されました。
呑山観音寺はそれ以来、第16番札所となり、篠栗八十八ヶ所の関所と言われるようになりました。
信仰を集める「祈りの寺」として、真言密教の修行の場として、
お大師様の精神はこの地で脈々と受け継がれています。
|